top of page

鳴門市

大代古墳群
古墳直下を通過
吉野川下流域、讃岐山脈南側の尾根上に分布する古墳群で、高速道路建設に伴って調査が行われました。当初は、消滅の危機であったが古墳群の下にトンネルを通すことによって保存されることになった。そのため、古墳の墳丘に登ると眼下に高速道を行きかう車の珍しい光景を目にすることができます。
周辺域には、宝幢寺古墳群、萩原墳墓群、天河別神社古墳群などが分布しており、「鳴門板野古墳群」と総称される。
主墳である前方後円墳は、全長54mを測り、埴輪、段築、葺石を備えます。また、前方部南側と後円部北側には、掘割溝が存在し、それぞれに円墳が隣接します。埋葬施設は、南北7.4m、東西4.5mの竪穴式石室に、全長2.84m、幅0.87mの刳抜式舟形石棺が納められていました�。白色凝灰岩を用いた石棺は、徳島県立埋蔵文化財センターにレプリカが展示されております。
出土遺物は、獣形鏡、玉類、銅鏃、鉄鏃、鉄剣、鉄刀、鉄矛、長方板革綴短甲、鋤先、鉄斧、刀子、鉇、鉄鎌、鑿、円筒埴輪、朝顔形埴輪、形象埴輪などが出土。築造年代は4世紀末と推定される。
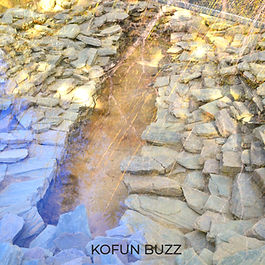
西山谷2号墳
水上交通を掌握
鳴門市大麻町、讃岐山脈南麓に位置した古墳で、6基から構成される古墳群に属していました。現在は、2号墳をレキシルとくしま(徳島県立埋蔵文化財総合センター)に移設し、屋外展示されています。
墳丘規模は、径18~20m、高さ2mの円墳です。埋葬施設は、長さ4.72m、幅0.83~1.05mの竪穴式石室に刳貫式木棺が納められていました。全国的にみても最古級の石室の一つとなっている。
出土遺物は、斜縁上方作銘獣帯鏡、鉄剣、鉄槍、鉄斧、鉄鏃、ヤリガンナ、直口壺、甕が出土。築造年代は、出土した土器から3世紀中頃と推定される。被葬者は、水上交通を掌握した首長墓の墳墓と考えられています。

ぬか塚古墳
豊富な副葬品が出土
樋殿谷川の左岸、丘陵南麓の扇状地に位置する古墳で、旧撫養街道と県道41号線が交差する南東の私有地に残ってます。
墳丘規模は、径30m、高さ5mの円墳となります。埋葬施設は、南に開口する片袖式の横穴石室で全長4.8m、玄室長3.34m、奥壁幅1.5m、中央幅1.7m、前壁幅1.6m、高さ2.4m、玄門部幅1m、羨道高さ1.6mを測り、胴張りの平面形を成します。石室石材は、玄室に砂岩、羨道部に砂岩と緑色片岩を用いている。
出土遺物は、銅鏡、鉄鏃、三累環頭太刀、単龍環頭太刀、金貼空玉、石製玉類、トンボ玉、鏡板、辻金具、カコ、雲珠、�轡、鐙、杏葉、馬鐸、馬鈴、須恵器など豊富な副葬品が出土する。築造年代は、6世紀後半と推定。

萩原移築古墳
宝幢寺境内に石室移設
吉野川下流域、大麻山南麓には、4基から構成される萩原墳墓群があります。そのうち1号墳の主体部である竪穴式石室や箱式石棺墓の一部を宝幢寺境内に移設保存しています。周辺域には、宝幢寺古墳群、大代古墳群、天河別神社古墳群などが分布し�ており、「鳴門板野古墳群」と総称される。
埋葬施設が移設されている1号墳は、現存長4m、幅1.25mの竪穴式石室を有し、墓壙を方形区画にて列石で囲っている。石室自体は、結晶片岩の割板石を用いて小口積みにしています。
墳丘は、円丘部径18m、突出部長8.5m、幅2.6m、くびれ部幅3.6mの前方後円形の積石塚で、周溝が巡っていました。出土遺物は、画文帯神獣鏡、管玉、弥生土器が出土。築造年代は、3世紀前半と推定される。
bottom of page






